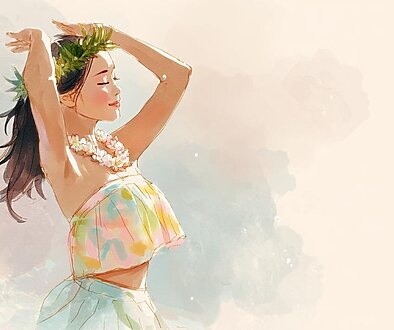日本人が知らないフラの常識5選|これを知らないと恥をかくかも?
日本人が知らないフラの常識とは?
フラを始めたばかりの頃、「なんとなく違和感を持たれた気がする」「ルールを知らなかったせいで恥ずかしい思いをした」──そんな経験をしたことはありませんか?
実は、日本ではあまり知られていないフラの“常識”や“文化的なマナー”がいくつか存在します。
今回は、ハワイの文化を尊重しながらフラを学ぶために、ぜひ知っておきたい「フラの常識」5選をご紹介します。
1. クム(先生)への敬意は“姿勢”で示す
ハワイでは、フラの先生である「クム・フラ(Kumu Hula)」に対する敬意がとても重視されます。
日本の感覚で「先生=友達のように親しみやすい存在」と捉えると、思わぬ失礼になることも。
たとえば──
- レッスン開始前に「ごあいさつ」をきちんとする
- 名前を呼び捨てにしない(「先生」「クム」とつける)
- 教えに対して反論したり、勝手に振付を変えない
こうした基本姿勢が「学ぶ側の礼儀」として根づいています。
2. パウスカートは“神聖なもの”
フラで着用するスカート「パウスカート」は、単なる衣装ではありません。
ハワイの伝統では、衣装にも“マナ(spiritual power)”が宿るとされており、パウスカートは神聖なものとされています。
そのため──
- 床に放り投げない
- 足で踏まないように気をつける
- 洗濯後の保管場所にも気を配る
心をこめて身につける衣装だからこそ、扱い方も丁寧にしたいですね。
3. チャンティングは儀式の一部
レッスンやステージ前に唱える“チャンティング”──ただの掛け声や挨拶だと思っていませんか?
実はチャンティングは「フラを踊る前の儀式」とも言える重要な要素です。
ハワイの伝統では、自然や神々と心をつなぐためにチャンティングが行われてきました。
無言で参加したり、ふざけたりするのは大変な失礼にあたるため、心を整えて参加するのがマナーです。
4. 動作の意味を“理解してから”踊る
フラはただのダンスではありません。
一つ一つの動きに物語や自然現象の意味が込められているのです。
だからこそ──
- 振付の背景を知る
- 歌詞の意味を調べる
- どんな自然・感情が表現されているかを理解する
これらは「振付を覚える」以上に大切なこととして教えられます。
意味を知らずに踊るのは、“中身のないフラ”になってしまうので、注意が必要です。
5. 発表会は“舞台”ではなく“奉納”
日本では発表会=ショーや披露の場という感覚が一般的ですが、フラでは少し違います。
もともとフラは神々への奉納や、自然への感謝を表現する「祈りの踊り」として始まりました。
現代でもその精神は大切にされていて、発表会もまた「感謝と祈りの場」としての意味合いを持ちます。
衣装や髪飾りに心を込めること、遅刻せず真摯に踊ること、
それらすべてがハワイの文化を尊重する姿勢につながっています。
フラは“文化を学ぶ”ことでもある
日本では「健康のためのダンス」「趣味のひとつ」として始める方が多いフラ。
でも、ひとたびその文化の奥深さに触れると、ただのレクリエーションではないことに気づきます。
ハワイ語、神話、自然観、人との関係性──
フラは文化そのものを踊るアートなのです。
だからこそ、マナーやルールを知ることは、その文化を敬う第一歩。
知らなかったことが恥ずかしいのではなく、学ぼうとしないことが“失礼”になるという感覚を、ぜひ大切にしていきましょう。